言い訳をしないアルテタがアーセナルに植え付けた勝者のメンタリティ
サッカー監督の記者会見では、時折解釈の難しい言葉が飛び交うことがある。監督は基本的にはあまり外部に情報を出したくないものだからだ。
だからこそ、私が注目するのは、監督が質問されたわけではないのに発する言葉だ。
その良い例が、ルートン戦でマンオブザマッチの活躍を見せたスミスロウに関してのコメントで、この時既にスミスロウの退団は既定路線となっていた。
アルテタは『彼はボールを持っていないときも今日は非常に良いフィジカルと走力を見せた。多くのデュエルに臨んで勝利したし、前でも何か起こそうと意図をもってプレイしたね』と話したが、これらの要素は質問の中では全く触れられていないものだった。
恐らくこれが、アルテタがこれまでスミスロウに欠けている、と感じていた部分で、そのような話を選手としたこともあったのだろう。
その一方で、監督が非常に明快なメッセージを会見で発することもある。
その良い例が、アルテタの監督就任会見だ。アーセン・ベンゲルのコミュニケーションは非常にわかりやすかったが、それはウナイ・エメリ期には言語力上の問題で少し失われており、ファン選手共に同様の印象を持っていたはずだ。
だが、アルテタは一度目の会見から、アーセナルの監督会見に再び明快さを取り戻させた。
さらに、これは自身のマニフェストの発表の場でもあり、そしてアルテタはそれを見事に実現させている。特に私が印象深く覚えているのがこの部分だ:
まずこのクラブを取り巻くエネルギーを変える必要がある。先週私はシティのチームとともにここに来たが、アーセナルの状況を目にして少し落ち込んでいた。全員にきちんとクラブと向きあってもらい、選手たちに私が何をしたいのか、そしてそれをどのように行うのか、納得してもらう必要がある。これまでとはやり方、考え方が変わるということを受けて入れ貰わなくてはならず、スタッフとアーセナルに関わる全員に同じ気持ちを持ってもらいたいんだ。
我々はカルチャーを作り上げなくてはならない。正しいカルチャーがなければ、難しい事態に陥った時に樹(クラブ)全体が揺らいでしまう。私の仕事はこれこそがアーセナルのやり方だ、というのを全員に納得してもらうことで、それはクラブの一員であるためには妥協できない点だということを理解してもらわなくてはならない。他は二の次だ。
特にこの『樹全体が揺さぶられてしまう』というフレーズは非常に印象的だった。
アルテタは監督就任直後、様々な整理を行う必要があったが、その中でもう一つアルテタがよく好んで用いたフレーズが『同じ船に乗っている』だ。
彼は選手に対して自身のビジョンにコミットすることを求めていた。クラブのカルチャーを変えたかったのだ。
今週のレアル・マドリード戦はアルテタが語った『クラブを取り巻くエネルギーを変える』というプロジェクトの集大成ともいえるものだった。
この日のアーセナルはアルテタが初日の会見で触れた、マンチェスター・シティにばらばらに引き裂かれてしまったチームとは全く異なった。
だが一方で、今季全体を見れば、ある程度『樹が揺さぶられた』シーズンだったのは間違いないだろう。何人かの選手はしがみつこうとしてハムストリングを負傷してしまったし、何人かの審判がグレネードも投げつけてきた。
これら全てはアーセナルにとってはどうにもできないことだった、と言いたいわけではない。特に選手層に関しては、直近の2回の移籍市場でアーセナルはもっと土台を固めることはできたはずだ。
とはいえ、今季のアーセナルとアルテタはかなり運がなかったと言えるだろう(もちろんこれはアーセナルにとってだけでなく、どのクラブにも起こりうることだ。直近何年かのリバプールの成績を見れば、どの年が彼らの樹が揺さぶられたのかを判別するのは容易い)。
だが、どのような困難が起きてもアルテタとアーセナルが一貫して冷静な姿勢を保ったのは賞賛されるべきではないかと思う。
今のアーセナルは爆発力や特に攻撃に関してはもう少し改善の余地や伸びしろがある一方で、多少不測の事態があっても動じることなく、ある程度のパフォーマンスを保てるチームだ。
もちろんそれは個人の資質も影響している。デクラン・ライス獲得に100mの移籍金が必要となった(今の彼にはその倍の価値があるかもしれないが)のには理由があるのだ。
だが、それだけが理由ではない。彼らのような才能あふれる選手たちをアルテタがどのように指導してきたも大きく影響している。そうでなければメリーノをトップに、18歳のルイス=スケリーを左サイドバックにおいてレアル・マドリードに3-0で勝利を収めることなどできるはずがない。
そして何より、これにはアルテタが強調したカルチャーの違いがものを言っている。監督の記者会見の話に戻るが、今季アルテタは公の場で決して今季のアーセナルが昨季より前に進むことが出来ていないことを、怪我のせいにすることはなかった。
最近たった一週間の間に最終ラインから4人ものけが人が出た時も、それは変わらなかった。
ここから我々は学ばなくてはならず、コーチングスタッフは何とか今の状況に対処しなくてはならない。選手はコーチや監督を見ているものだからね。もし我々がもう不可能だ、アンラッキーすぎる、と言い出してしまったら、そこで不可能になってしまう。選手たちがせっかく4月まで、そうならないような理由を与えてくれているんだからね。
上のコメントと、トッテナムにけが人が続発した時期のポステコグルーのコメントを比べてみて欲しい。彼は敗北を認め、主力が怪我から帰ってくるまではどうしようもないと述べた。
アルテタは、怪我のせいでアーセナルが昨季ほどリーグ優勝に近づけていないとコメントすることもできたはずだ。恐らく、心の中ではそう思っているだろう。
だが、会見など公の場ではそのようなことを口にすることを彼は拒み続けており、そして、それはきちんとした理由あってのことだ。彼はアーセナルが言い訳をしたり、被害者のように振舞ってしまうカルチャーを作らないようにしているのだ。
少し前に、サカが相手チームから多くのファウルに晒された時期に、これに関して質問されたことがあったが、アルテタはこれについても、不満を言ったり、自チームの選手に対して過度に保護的なコメントをすることはなく、『サッカーにはフィジカルコンタクトはつきものだからね。特に相手を1対1で突破しようとするウイングにはこれはよくあることだ。彼はもう慣れてきていると思うよ。』と話したのみだった。
今季のリーグ優勝争いに関しても、もう既に実質的には終わってしまっている、というのはアルテタ自身もわかっているに違いないが、それでも少し前に彼は『そのように考えるのであれば、もう私はこの仕事を止めてしまった方がいい』とコメントしていた。
このような姿勢は、今季というよりむしろ、カルチャーを植え付けることを通じて、来季やより先の将来に意味が現れてくるのだろう。
今季アーセナルは大きく揺さぶられたが、アルテタがアーセナルに植え付けたカルチャーがレアル・マドリード戦のような結果を生み出した。
まだデビューして30試合しかプレイしていない18歳の若者が左サイドバックの位置からレアル・マドリードを制圧し、29歳にして初めてFWにトライする選手が柔軟に進化を遂げ、デクラン・ライスが2本のFKを決め、歴史に残る勝利にチームを導いた。
困難に襲われた時でさえも、アーセナルは強固な信念を失うことなかった。これこそがミケル・アルテタが、戦術やチームに留まらず、アーセナルのクラブとしてのカルチャーを変革することに成功した証なのだ。
source(当該サイトの許可を得て翻訳しています):


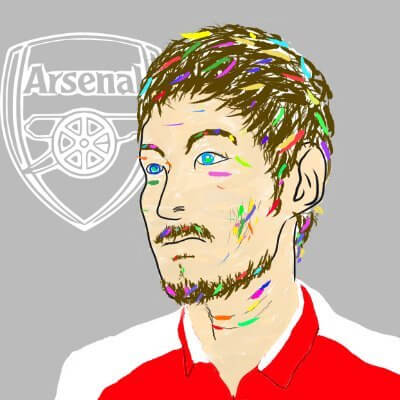

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません